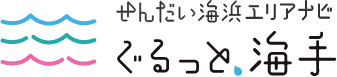つながりから⽣まれる、
集いの海辺未来へつなぐ、ひと。


仙台市宮城野区にある岡田地区新浜の住民は、東日本大震災の津波被害を受けた後、福田町の仮設住宅に身を寄せ合いました。そこに住民の憩いの場をつくろうと立ち上がったのが、「せんだいメディアテーク」の設計をした建築家・伊東豊雄氏でした。伊東氏がコミッショナーを務める熊本県の文化事業から「くまもとアートポリス東北支援《みんなの家》プロジェクト」が発足。今回は、当時を知る平山一男さん、震災後、新浜で畑を借りながら、貞山運河沿いの自然や文化を大切な資源として紹介する活動を続ける上原啓五さんと、新浜に魅了され二人とともにさまざまな活動に参加するアーティスト・佐々瞬さんに話を伺いました。
地域コミュニティを守り、
心の支えとなった「みんなの家」

新浜の人たちが集まる憩いの場「みんなの家」には、危機が二度あった。
一度目は、「みんなの家」の建設が始まる前。福田町南一丁目公園に設置された仮設住宅の一画に、新浜の人たちが集える場を作ってはどうかという建築家・伊東豊雄氏の提案を、住民はすぐに受け止められなかった。震災から3か月しか経っていない6月、仮設住宅に入居した直後の出来事だったからだ。しかし、「もういちど話を聞いてみよう」と平山さんが呼びかけ、2度目の訪問を受け入れ、考えを改めた住民たちの優しさが、「みんなの家」の原点である。ほどなく建設が決まり、7月末には地鎮祭が行われ、2011年秋に完成した。
二度目は仮設住宅の閉鎖が決まったとき。「みんなの家」も閉鎖するか、それとも別の場所に移築するかの検討が行われた。移築するには土地を借りなければならず、調整の難しさに住民は頭を抱えた。最終的には、仙台市役所が新浜へ移築すると決定し、2017年4月に、伊東豊雄氏をはじめ、くまもとアートポリスの方々もお招きし、現在の場所での再開をともに祝うことができた。
住民同士のコミュニケーションの場としてなくてはならないものとなった「みんなの家」は二度の危機を乗り越え、現在、新浜で活動する際の拠点にもなっている。地域の人々が集まる「みんなのカフェ」や、さまざまなワークショップも開催されるほか、イベントの集合場所・休憩場所としても重宝されている。
貞山運河の風景に魅了され、長年その魅力を発信し続けてきた貞山運河倶楽部の代表・上原啓五さんは、建物自体のデザインが新浜にマッチしていたと話す。「どこか懐かしい素朴な外観に、畳敷きの小上がりや薪ストーブ、色とりどりの花が咲く花壇、住民たちの意見を取り入れて造られたからこそ、愛着も湧きます」。

アーティストとタッグを組んで
新浜・貞山運河の魅力を発信

「みんなの家」は地域住民が気軽に集まれる場所としてだけでなく、新浜でイベントなどが行われる際のハブとしての役割も担っている。地元で活動するアーティストが参加する「貞山運河小屋めぐり」も、「みんなの家」を拠点に開催されるイベントの一つだ。現在は年に4回開催され、貞山運河の周辺に設置された小屋をめぐる。「これまでに《盆谷地の小屋》と《小屋のような田んぼ》の二つの小屋をつくりました。せんだいメディアテークに勤務していた頃に平山さん・上原さんと出会い、交流を続けてきた縁ですね」と参加アーティストの佐々瞬さんは話す。
現在新浜には12の小屋が点在している。「みんなの家」や、隣接する「となりの畑の小屋」もその一つに数えられる。

だが、なぜ「小屋」なのか。
これについて上原さんは、「新浜やその周辺地域は農業が盛んでした。農業には機材置き場や休憩所となる小屋が欠かせません。地域に溶け込みやすく、イベントがなくても見に来ることができる。何かおもしろいものがあるぞ、と新浜に来るきっかけになるのではないかと思いました」と語る。
小屋には隠れ家的な魅力もある。その小屋を参加者全員で歩いて見て回り、新浜の「少し変わったおもしろさ」を体感し、感じたことや思ったことは「みんなの家」に持ち帰ってみんなで共有する。そうしてできた人と人、人と新浜のつながりが、地域の賑わい創出につながっていく。そこには「また来たい、住んでみたいと思ってもらえるように」という想いが込められている。「佐々さんのようなアーティストやクリエイターの方々はおもしろいアイデアを次々出してくださる。そのアイデアを生かしていけば、新浜はもっといいまちになると思うんです」。
上原さんがそう思うきっかけの一つとなったのが、世界的に活躍するアーティスト・川俣正氏によるプロジェクト「仙台インプログレス」だ。津波で被災し、橋が流され貞山運河を渡ることができなくなってしまった新浜地区の住民のため、「みんなの橋」設置に向けて活動が続けられている。橋を架けるにはしがらみが多く一筋縄ではいかないが、取り外しが容易な吊り橋を作ったり、運河まで続く木道を作ったりしていくうちに、上原さんはランドアート的な楽しみ方を見出した。
ランドアートは1970年代に流行した考え方で、アート作品が景観に自然と溶け込み、気付かない間に人々に親しまれているところが魅力だという。単一的な彫刻やモニュメントではなく、貞山運河の素晴らしい景観にそっと寄り添い、同化するような作品が求められている。

全ては昔の賑わいを取り戻すため
未来を切り拓くアートの力

「みんなの家」そして新浜地区の今後について三人に語っていただいた。平山さんは、特に地域住民の方々に貞山運河や新浜の魅力と向き合ってほしいと話す。「イベントの仕掛けもみんなの家も、これまで積み上げてきたことを変わらず続けていきたいと思っています」。
その想いを引き継ぐ佐々さんは、アーティストならではの視点で新浜のまちづくりの可能性を模索している。その一つが陶芸だ。「海辺の土は陶芸に向かないと言われているのですが、新浜の湿地の粘土を使って器作りに挑戦しています。砂浜の砂を釉薬にすることで新浜でしかできない体験が可能になる。試作には成功したので、焼き窯を安定させ、地域の方々が楽しめる陶芸教室を開催することで、自分の地元の魅力に気付いてほしいなと思っています」。
ランドアートに並々ならぬ情熱を燃やす上原さんだが、「みんなの家」に隣接して作られた「となりの畑」のことも忘れてはいけない。「野菜づくりは天候に左右されやすく、良い野菜をつくるのは難しい。おいしい野菜ができたときの達成感は何にも代えがたいもの。その喜びを感じてもらえるよう、畑を通した農業指導にも力を入れていきたいと思っています」。
震災直後は地域コミュニティの要だった「みんなの家」は、土台となる考え方をそのままに、アートによるまちの賑わいづくりのシンクタンクとしての役割を担っている。根底にあるのは、平山さんのようにかつての新浜を知る住民たちの「昔の賑わいを取り戻したい」という純粋な想い。
新浜・貞山運河とアートがどんな化学反応を起こし、まちの未来を切り拓いていくのか。これからを楽しみに待ちたい。

ほかのインタビューを読む
-
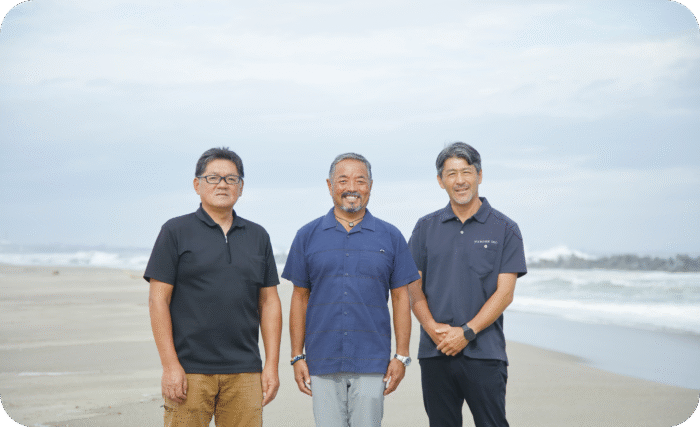 深沼海水浴場運営協議会
深沼海水浴場運営協議会
会長 今野 幸輝さん 副会長 村川 琢哉さん 幹事 末永 薫さんサーフィンに夢中だった 少年の頃から慣れ親しんだ 海辺の景色を取り戻すために -
 「NPO法人みちのくトレイルクラブ」事務局 板谷 学さん震災を語り継ぐ 全長1,000kmを超える 「みちのく潮風トレイル」
「NPO法人みちのくトレイルクラブ」事務局 板谷 学さん震災を語り継ぐ 全長1,000kmを超える 「みちのく潮風トレイル」 -
 アクアイグニス仙台 支配人 平間 雅孝さん可能性は無限大 新たな一歩を踏み出す藤塚に 癒やしとにぎわいを
アクアイグニス仙台 支配人 平間 雅孝さん可能性は無限大 新たな一歩を踏み出す藤塚に 癒やしとにぎわいを -
 「フカヌマビーチクリーン」事務局 庄子 隆弘さんきっかけとしての 海岸清掃活動 「深沼ビーチクリーン」
「フカヌマビーチクリーン」事務局 庄子 隆弘さんきっかけとしての 海岸清掃活動 「深沼ビーチクリーン」 -
 新浜町内会 副会長「みんなの家」管理人
新浜町内会 副会長「みんなの家」管理人
平山 一男さん 貞山運河倶楽部 上原 啓五さん アーティスト 佐々 瞬さん小屋=アート作品 新浜・貞山運河に秘められた ランドアートの可能性